

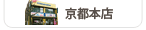
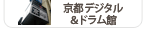
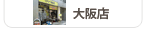
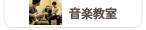
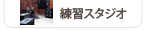
|
|
初心者も安心!難解な「DTM用語」を一挙に解決! 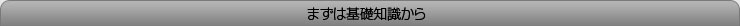 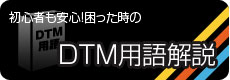
初心者も安心!困った時のDTM用語解説
DTM機器等を調べていると良く意味の分からない言葉に出会います・・・。そんな言葉のうち「特にご質問の多い」言葉を一挙に解説してます! 随時更新していますので、たまにはご覧下さいね!」 「DTM一般用語」について:DTMという専門分野で使われる言葉を中心にご案内。 「コンピュータ用語」について:DTMの根本でもあるコンピュータの専門用語をご案内。 「入出力関係用語」について:コネクタの名称など、DTMに関わらず音楽機材の用語をご案内。 ※こちらに掲載の内容は簡潔に説明する事を目的としているため、一部箇所は語弊の伴う表現があります。 ご参考までにご覧頂けますよう予めご了承下さいませ。
DTM
「デスクトップ ミュージック」の略。パソコンを使用した音楽の事や音楽制作を表します。正確な意味合いは色々なところで賛否両論ありますが、コンピューターミュージック的な捉えで良いと思います。
DAW
「デジタル オーディオ ワークステーション」の略で、コンピューターでオーディオやMIDIを使用して音源・エフェクトを操作し、ミキシングや書き出しまでの一連の作業ができる一環システムの事を表します。
インターフェース
コンピューターと楽器等の間の「情報のやり取り」を仲介する機器の事。厳密には「オーディオ・インターフェース」、「MIDI・インターフェース」、さらには「オーディオMIDI・インターフェース」等があります。
オーディオ
コンピューター上での音声データ(.wavや.aif等)の事。テープで録音されたものを想像頂 ければわかりやすいと思いますが、「オーディオ」は基本的に「テンポを変えずに音程を変える」、「音程を変えずにテンポ(BPM)を変える」といった事ができません。でも、高性能なDAW程それが自由に行えます。
MIDI
音楽で使用される事を基準とした「命令信号」の事。MIDIはオーディオと違い、それそのものに音声は含んでいません。例えば、MIDI出力できる鍵盤には「ド」の位置に「ドの命令信号(MIDI)」が割り当てられており、その信号が音源ソフトに伝 わって「ド」が鳴る仕組みです。従って鍵盤の送信信号を変えたり、音源の受信信号を変えた場合はミを押してドを鳴らす事等ができますし、DAW上で MIDI打ち込んだ場合、楽曲完成後に再編集する事等が容易です。
プラグイン
DAW上で音源ソフトを立ち上げる際に定められた規格。もしくは立ち上げられるソフトウェアを総称する際に使われます。 VST、RTAS、AudioSuite等色んな規格があります。。
スタンドアローン
DAWを必要とせずそのソフトのみで立ち上がる事をさします。「スタンド(立つ)アローン(一人)」なので、独り立ちって事です。
サードパーティ
特定のブランドのものに対して、そのブランドとは別のブランドのものの総称。「Cubase」に対して「BFD」はサードパーティ。「Cubase」に対して「The Grand」はサードパーティではない、という事になります。
アクティベーション
製品登録のこと。ほとんどがオンライン・アクティベーションで、その作業方法は製品ごとに異なっているので不明な場合はすぐにメーカー等へ聞きましょう。 ちなみに、"オーソライズ"も同じ意味と思って頂いて問題ありません。
動作要件
使用する為に最低限必要とするシステムの要件です。満たしていない場合、メーカーサポート等を受けられない場合が多いので必ずチェックしましょう。
アウトボード
アナログ・ハードウェアエフェクター等の総称。当然アナログ機器なので、デジタルで編集した音楽を通す事でヴァーチャルソフト等では再現できない事実上のアナログ的なサウンドを加味/変質させる為に使用する事が多いです。
キロヘルツ
「kHz」などで表され正式にはサンプリング周波数と呼ばれます。CDクオリティは 44.1kHzですが、これは1秒間を44100個に刻むという事です。 よってサンプリング周波数だけでみた場合、数値が大きい程アナログ音声に近い信号 で分断できます。 サンプリング周波数は「量子化ビット数」と深い関わりがあるので合わせて「Bit」もご確認下さい。
Bit
サンプリング周波数で刻まれた情報を何段階に分けて「数値化」するかを表します。よって数値が大きい程アナログ音声に近い信号でデジタル化できます。 正式には「量子化ビット数」の事で周波数と関わりが深いので「キロヘルツ」も合わせてご覧下さい。
AD/DA
「音」は振幅の連続なのですが、アナログがサイン波的な形をしているのに対しデジタルはスクエア波的な形状になります。要するに根本的に相違があるのですが、この「アナログ」と「デジタル」を相互変換する事/部位をさす事が多いです。
dB(デシベル)
基準値に対しての聴感値。音響的には0.775Vrms(rmsは実効出力)を0dBとされています。フェーダーは0dB付近で使うのが一番良いというのは0dBから離れると個体の音質劣化/変化がおきるためです。 TOPに戻る
CPU
コンピューターは計算の連続で動いているものですが、その計算自体をするコンピューターのパーツです。DTMの動作要件ではIntel製のCPUを指す場合が多く、お手持ちのCPUが「AMD」などのIntel以外の場合は要注意です。
メモリ
CPUが計算をする所であれば、メモリはその計算されるものや計算後のものを「一時的に置く」テーブルのようなものです。記録媒体として転送スピードはハードディスクより高速ですが、ハードディスクよりは小さいのが一般的です。
ハードディスク
メモリ同様、記録媒体ですがメモリの項で説明の通り大容量でメモリより低速です。例えるなら「引き出し」。データは、ハードディスク→メモリ→CPU→メモリ→ハードディスクという流れが一般的です。
レイテンシー
ハードディスクの項で示した通り、データは「流れ作業」なのですが、その「流れ作業」にかかる 時間が影響し、「ギターを弾いてから鳴る」までの時間差が起きる事が、レイテンシーです。CPUの演算処理速度やインターフェース(USB1.1)が原因となるのは勿論、ハードディスクの転送速度 が影響している場合も多いです。
OS
「オペレーティング・システム」の略。実はWindowsやMacはある複雑なプログラムのアプリケーションで、実際の命令などを司っているのは複雑なプログラムの方です。そのプログラムをマウスを用いて「視覚的・感覚的に操作する」という事を実現しているのがOS(WindowsやMac)。文字羅列ではなく画像やアイコンをクリックして作業できるのはOSのおかげ、という事です。
PDF
DTMソフトの中にはマニュアルが冊子で用意されておらず、この「PDF」ファイルで収録されています。「Adobe Reader」というソフトで開く事ができ、無償でWebよりダウンロードできます。
ドライバ
コンピューターで対象機器を認識させる為に必要なソフトウェア。簡単にいうと、「接続機器」が自ら"私はオーディオインターフェースですよ"といってくれない限りコンピュータにとっては何が接続されたかわからないので、"彼はオーディオインターフェースですよ"と教えてあげるためのソフトウェアが「ドライバ」です。 悩ましいことは、OSを含む「ソフトウェア」は日進月歩している為、パッケージに封入されたドライバCDは古い場合が多い事。 なるべくは機器のインストール前に、メーカーから最新のドライバをダウンロードする事をお勧めします。
バスパワー
コンピューターから電源供給される事。インターフェースやMIDIコントローラに多く、「バスパワー対応」であればアダプタ等を必要とせずコンピューターとの接続で電源を供給できます。
プラグアンドプレイ
機器をコンピューターに接続するだけで利用できる事。一般的にはコンピューターに機器を 認識/動作させる為に「ドライバ」が必要ですが、プラグアンドプレイの場合、OSに付属されたドライバを使用するため、ドライバのインストール作業が不要! ※OSが 一般的で無い場合やOS付属ドライバが何らかの形で無くなっている場合は、認識できない事もあります。 TOPに戻る
USB
「Universal Serial Bus」の略でコンピューターに機器を接続する際に使用する規格。現在もっとも普及している規格で転送速度順に「USB1.0」、「USB1.1」、「USB2.0」があります。
FIREWIRE
「IEEE1394」が正式名称。コンピューターに機器を接続する際に使用する規格です。Firewireには400規格と800規格があり、400規格はUSB2.0とほぼ同等の転送速度を誇ります。 800規格は文字通り400規格の2倍の速度を誇り、より高速なデータ転送が実現出来ます。
フォン
ヘッドフォンやギター等で一般的な端子の事。一般的には2極(モノラル)のTSフォンと、3極(ステレオ)のTRSフォンがあり、サイズ径では標準(6.3mm(1/4inch))とミニ(3.5mm)がある。「1/4 TRS」等と記載されている事がありますが、この場合は要するに「標準ステレオフォン」という意味になります。
TRS
3極(ステレオ)の「フォン」と呼ばれる端子の事。詳しくは「フォン」項目をご確認下さい。
RCA
オーディオコンポやDVDプレーヤ、DJ機器等の家電機器で一般的な「あか・しろ」コネクタです。ピンとか呼ばれる場合もあります。 怖いのはRCAはアナログだけでなくデジタルにも採用されており、見た目は同じでもアナログ接続としては使えないので注意! デジタルの場合はS/PDIF、もしくはコアキシャル等と表記されています。
XLR
ごっつい形状の、マイク接続等で一般的なコネクタです。アメリカのCannon社が開発したので「キャノン」とか呼ばれます。 コンデンサー・マイクへの電源供給(ファンタム電源供給)はこのケーブルを介して行えます。 ちなみにアナログ接続だけでなくデジタル接続でも使用されている事があり、見た目が同じでも「AES/EBU」等と表記がある場合はアナログ接続としては利用ができませんので要注意。
ワード・クロック
デジタル伝送ではケーブル等を介して機器同士を接続し、一定のルールに従うよう「同期」した上で動作する仕組みになっているのですが、この際に使用される同期信号をワード・クロックと言います。同期機器の間には「マスター」に「スレーブ」を同期させる、といった形で主従関係を設定して使用します。 マスターをどれにするかでデジタル伝送の精度が変わるので、デジタル伝送の際には非常に重要。
ADAT
プロ業界等で広く使われているデジタル入出力規格の事。1本のケーブルで8CHもの入出力を実現でき、現状で様々な機器に搭載されている為、レコーディング業界では広く浸透している規格です。ちなみに形状はS/PDIFの角形コネクタと同じですが、情報自体は全くの別物ですので要注意。
AES/EBU
プロ向け(業務用)のデジタル伝送規格のひとつ。1回線で2ch使用できる事が特徴で一般的にはXLRコネクタを使用します。尚、マルチチャンネルの場合はD-Sub25コネクタ等を使用する場合もあり、この場合ケーブル1本で8chの入出力を実現できますが、D-Sub25のピン配列がメーカーごとにバラバラだったりするので、要注意。 ちなみに、「S/PDIF」はAES/EBUの伝送構造を使用した民生規格として登場していますが、AES/EBUとは互換性が無いので要注意です。
S/PDIF
「AES/EBU」の伝送規格を簡略化したデジタル伝送規格。SONYとPHILIPSが共同開発し、民生規格としてコンポ等でも広く採用されてます。光ファイバーケーブルを使用する「オプティカル」とアナログ音声で定番のRCAコネクタを使用する「コアキシャル」があり、「オプティカル」には角形コネクタと丸形コネクタがあります。「コアキシャル」の場合、見かけはRCAそのもですが、伝送内容が全く異なるので要注意。
マイクプリ
マイク・プリアンプの事。マイクからの信号は小さな信号である為、増幅する必要があるのですが、その増幅器がマイクプリアンプ。マイクそのものは勿論ですが、このマイクプリでも音質が劇的に変わるのでギタリストのアンプ選びのような、音楽的な楽しみの一つでもあります。
ファンタム電源
コンデンサーマイクには電源供給が必要ですが、マイクプリ等からマイクケーブル(XLRケーブル)を通して供給する方式の事。
PAD
民生用機材は-10dB、業務用機材は+4dBを基準に音声信号のやり取りがされているのですが、ライン入力(Hi)の場合は+10dBを基準に音声信号が発信されているため、普通に入力信号を受けただけでクリップ(音割れ)が起きてしまいます。そこで、クリップは勿論、使いやすくするために強制的に入力レベルを落とすのがPADです。 TOPに戻る
|